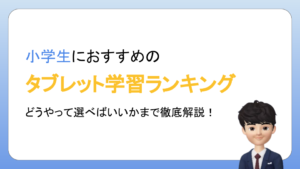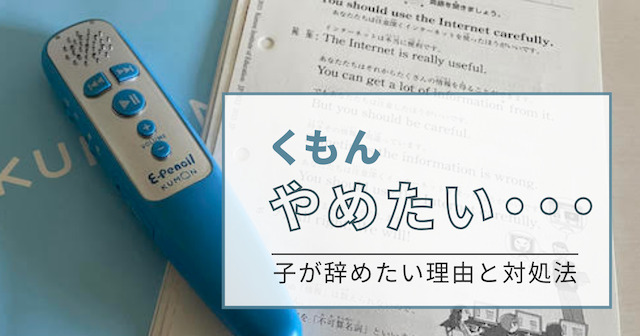- 公文をやめたいと子供が言っている…
- 公文の効果に疑問を感じている
- 具体的にどうしたらいいか教えてほしい
「公文をやめたい」とお子さんが言ってきたらショックですよね。しかしせっかく続けてきた公文をやめてしまっていいのかは迷う方も多いと思います。
私は公文の利用歴7年で、4人の子どもを通わせましたが、親目線でも公文を続けようか辞めようか、迷う場面は少なからずありました。

支払った金額、送迎の労力、公文をやったかどうかの声がけなど精神的負担、子どもの勉強時間の大半を公文に費やしても良いものか…といったことを考えると、効果が見合っているのか疑問に思うのも無理はないでしょう。
親のそうした気持ちが先か、子どもの「辞めたい」が先か、ご家庭によって違いがあるでしょうけれど、「公文大好き!早く公文に行きたい!」という子どもは少数派ではないでしょうか(羨ましいです…)
 まみぃ
まみぃ 元塾講師むらなか
元塾講師むらなか公文をやめたいと子供が言う理由
公文を辞めたいと思う理由も様々です。
ここでは、公文を辞めるよくある理由をまとめます。
- 宿題が多すぎるから
- 教室の時間が長いから
- 同じ問題ばかりでつまらないから
- 先生が好きじゃないから
- カリキュラムが難しいから
- 通信教育がやってみたいから
理由①:宿題が多すぎるから
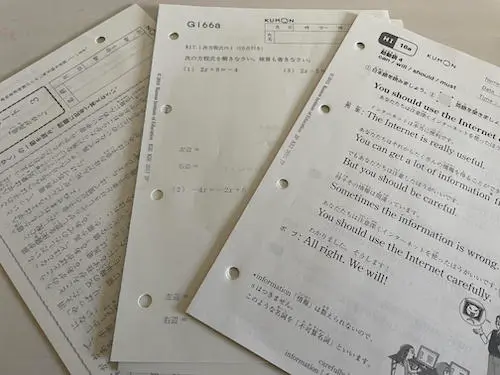
 元塾講師むらなか
元塾講師むらなか公文は基本的に、公文に入学した時の学年より2学年ほど下から学習をはじめます。
そのため、「簡単だからこれくらいできるよね」ということで最初の宿題の量を多く設定しがちです。
学校の宿題に加えて、公文の宿題もやらなければならないとなると、お子さんにはかなりの負担になりますよね。
以下の口コミのように、「宿題の量を減らしてもらった」というお子さんもいらっしゃるようです。
長男も公文数学辞めたいといっていたが、先生との話により、量を減らしてやることにしたらしい。やるなら自分で責任をとるようにと言った。ママはいつも宿題やったのかというストレスから解放されたい。
— takeko (@takeko1653) August 30, 2010
お子さんが「公文をやめたい」と言っているなら、まずは宿題の量が適量かどうかから見極めるのが良いでしょう。
理由②:教室の時間が長いから

公文の教室では、自力でプリントを解かなければなりません。
学校が終わったあとも、集中しなければならないので、疲れる子もいるでしょう。
そして、受講している教科が多い場合は特に、教室での滞在時間も長くなりがちです。
 まみぃ
まみぃ理由③:同じ問題ばかりでつまらないから
公文では反復学習を大事にしています。
 元塾講師むらなか
元塾講師むらなか公文の教材はシンプルな紙の教材なので、子供も見た瞬間に「あ、また同じだ」とやる気がなくなってしまいがちです。
しかしそれだけで公文をやめてしまうのはもったいないことです。
以下のツイートのように、同じ問題を完全に正解するまでやらされるのは辛かった、振り返るとあれは大切だった!と述べている人もいます。
あらきだ、公文を小学生の時にやってたんですが
何度も同じ問題を完全に正解するまでやらされるんですよね…
当時は何でだ?って思ったけど
あれは『次のステップに進んだときに困らない力をつけるため』だったんですよね— あらきだ (@arakidadada) March 22, 2022
反復学習の大切さをお子さんに理解してもらうのは中々難しいかもしれませんが、成長痛だと思って、もう一踏ん張りしてほしいです。
 まみぃ
まみぃ理由④:先生が好きじゃないから
勉強すること自体は楽しくても、公文の先生が苦手で、公文に行きたくないと言っている可能性も考えられます。
 元塾講師むらなか
元塾講師むらなか対面で先生に教えてもらえるのが公文のメリットですが、それは逆にデメリットにもなりえます。
「先生が好きじゃないから公文をやめたい」と思うこと自体はおかしなことではないので、お子さんの気持ちに寄り添って、次の行動を考えてあげましょう。
理由⑤:カリキュラムが難しいから
単語のだけの絵カードは楽しく復唱するんだけど、公文の2語文のやつになると、途端に無言。
大人からしたらそんな大差ないように思うんだけど、息子は明らかに「ダメだ…。難しすぎる…。」みたいな困った顔してる😢— ぽんママ (@ponmama_543) February 9, 2022
カリキュラムが難しすぎて、問題が解けない→つまらない→公文をやめたい、という事態に陥っている可能性も考えられます。
 元塾講師むらなか
元塾講師むらなか「問題が難しすぎる!」あるいは「問題が簡単すぎる!」という不満がある場合は、カリキュラムの設定がうまくいっていない可能性が高いです。
 まみぃ
まみぃ まみぃ
まみぃ理由⑥:通信教育がやってみたいから
好奇心旺盛な子にありがちなのが、話題の通信教育をやってみたいから、今続けている公文をやめたいという理由です。
 元塾講師むらなか
元塾講師むらなか公文をやめたいと子供が言ってきた場合の対処法
お子さんが「公文をやめたい」と言ってくる理由について説明したうえで、ここからは具体的な次のアクションについて紹介します。
- しばらく休む(サボる)
- 宿題の量やカリキュラムの変更をお願いをする
- 休会を申込む
- 公文の通信学習に切り替える
- 公文を辞める
対処法①:しばらく休む(サボる)
 元塾講師むらなか
元塾講師むらなか以下の口コミのように、「休んだら気が晴れて宿題をやるようになった」というお子さんもいらっしゃるようです。
昨日次男が珍しく「公文の宿題やりたくない、もうやめたい」て言うから、休めばいいじゃん、長く続けるためにサボりが必要な時あるし大人だってそうだし、みたいなこと言ったらなんか気が晴れたみたいで宿題もやってた。いやー上手く対応できてよかたわー思ったけど、
— 垂直 (@hori_gotatsu_) January 26, 2020
休むことで心機一転して、また公文に通いたい気持ちが湧いてくる可能性があります。
対処法②:宿題の量やカリキュラムの変更をお願いをする
宿題の量が多かったり、カリキュラムの内容が合っていないと感じている場合は、その旨を公文の先生に相談してみましょう。
 まみぃ
まみぃ公文の教室での時間が長いから辞めたがっている場合は、終わる時間について相談するとよいでしょう。
 まみぃ
まみぃ対処法③:休会する
公文をずっと休んでいると月謝がかかります。長期間通わない場合は、休会の申込みをしておくのがおすすめです。
休会や退会などの諸手続きの詳細は公文の公式サイトから確認してください。

休会中は月謝はかかりません。最大3ヶ月間休会することができます。
復会の申し出がなければ4ヶ月目から自動的に退会となる点には注意しましょう。
対処法④:公文の通信学習に切り替える

公文では、2020年頃から通信教育形式のサービスを提供するようになりました。月1回、担当指導者による採点および「通信学習連絡帳」でのコメントのやりとりを通じ、個人別に学習をサポートしています。
■現在、公文式教室で学習中で、これから通信学習を検討される方へ
各教室で通信による指導を行っている場合があります。お通いの教室にご確認ください。引用元:公文式通信学習
料金的には、同程度か若干高くなるようです。だったら通った方が学習効果は高そうですが、完全に辞めてしまうよりは、通信にして様子を見るのもアリかもしれません。
対処法⑤:退会する
 元塾講師むらなか
元塾講師むらなか子供にあまりやる気がないとき、無理にやらせるという考え方を、変えるべきだと思います。
やる気が出ないからといって、安易に公文に行かせて、勉強時間を増やしたとしても、能力が伸びるわけではありません。
結局、子供が勉強嫌いになったり、自分から学んでくれなかったりするのは、その学び方が本人と合っていないからです。
本人が自分から少しでも前向きになるようなやり方を提案すれば、やる気になってくれるはずです。
結局ズルズルと向いていない公文にそのまま通うことになってしまうと、時間もお金も無駄になってしまいます。
 まみぃ
まみぃ公文をやめたい相談は公文側にしてはいけない

よくある話ですが、担当の先生に「子供が公文を辞めたいって言ってて…どうすればいいのかアドバイスください」と相談する方がいます。
これは基本的にはおすすめしません。
なぜかというと、「この子は別の塾のほうが向いている」と塾の先生が思っていてもまさか「あなたのお子さんは公文に合っていないから他の塾に行ったほうがいいですよ」とは、なかなかアドバイスできないからです。
公文や塾に学習相談をしても、本当に子供のために思って言ってくれているのか判断しづらいです。なぜかと言うと、みんな自分たちにお客さんを呼びたいからです。
 まみぃ
まみぃ公文をやめて他の学習方法に変えるのも1つの手
公文を辞めた場合、勉強はどうすればいい?
私は公文の大きな魅力の1つは、無学年式にあると思っています。
実際のところ、子どもを公文に通わせて親として1番良かったと思うことは、先取り学習にあります。
特に中学生以降は、学校の授業についていけなくなるお子さんも多くなると聞きます。その点、先取りをしておくと、その効果を貯金のように実感する場面が出てきます。
そうした点を重視して、私はタブレット学習の「すらら」をおすすめします。

有名どころだと、進研ゼミのチャレンジやスマイルゼミでも無学年式を取り入れていますが、あくまでもサブ的位置づけであって、メイン教材は実際の学年がベースとなります。無学年で学習できる範囲も限定的なので、公文の代わりにするのはどうかなぁという印象です。(無学年式の学習にこだわらないのであれば別ですし、良い教材です)
その点「すらら」は、メイン教材が完全無学年式なので、求めている学習方法に合致します。料金的にも、国・数・英で公文の1教科分程度なので、コスパが良いです。(5教科コースもあり)
公文の代替としては、かなり有力な候補だと思います。無料で資料請求もできますから、検討してみてはいかがでしょうか。
\7月は入会金無料/
資料請求・無料体験受付中