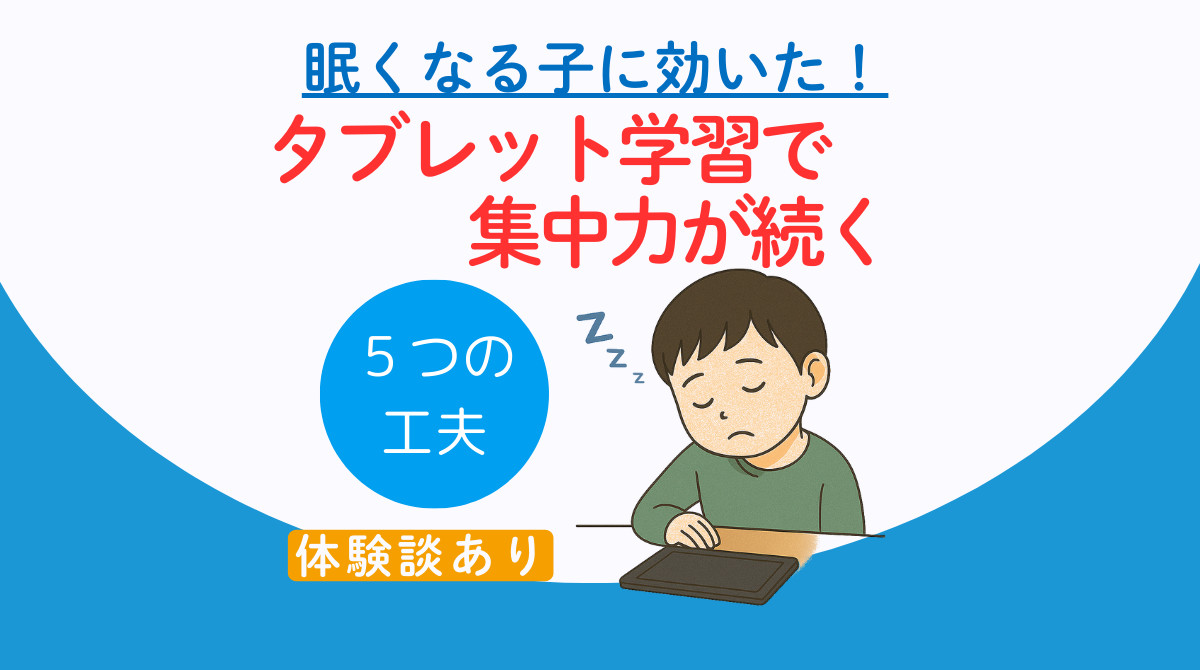タブレット学習は便利で柔軟な学び方ですが、静かな環境や単調な画面の操作が続くと、どうしても眠気が襲ってくることがあります。
特に自宅学習では、周囲の刺激が少ないため、子どもがうとうとしてしまうことも珍しくありません。
筆者自身も、子どもの学習をサポートする中で、「途中で眠くなって集中できない」と悩む場面を何度も経験してきました。
この記事では、特に効果を感じた「噛む」対策に加え、眠気対策として有効な工夫を複数紹介します。
なぜ学習中に眠くなるのか?

1. 視覚刺激の単調さ
タブレット学習は、紙の教材と比べて目の動きが少なく、画面を注視する時間が長くなるため、視覚刺激が単調になりがちです。
この視覚刺激の乏しさが、眠気を引き起こす一因となります(参考:日本眼科医会「目の疲れと学習への影響」)。
2. 姿勢や環境の影響
リビングや自室など、リラックスしやすい環境で学習していると、姿勢が崩れたり、血流が滞ったりして眠気につながることもあります。
特に暖房の効いた空間などは、身体が温まりすぎて眠気を誘発します。
3. 食後・夕方の学習タイミング
食後や夕方は生理的に眠くなりやすい時間帯です。
血糖値の上昇や体内時計の影響が関係しているため、無理に集中しようとしても逆効果になることがあります(参考:日本睡眠学会「睡眠と覚醒のリズム」)。
実践!眠気を吹き飛ばすおすすめ対策

1. 「噛む」で脳を刺激する
「噛む」という動作には、科学的にも脳を刺激し、集中力を高める効果があることが示されています。咀嚼によって脳幹網様体が刺激され、覚醒状態へと導かれやすくなるといわれています。
「噛むことで前頭前野や海馬の活動が高まり、作業記憶や集中力の向上につながることが示されています」(引用元:量子科学技術研究開発機構「ものを噛む“チューイング”、脳の作業記憶が向上」)
また、ロッテ「噛むこと研究室」では、名古屋女子大学の久保金弥教授監修のもと、「咀嚼が大脳皮質や海馬を刺激し、記憶力・集中力・ストレス軽減に効果がある」と紹介されています。
▷ 氷を噛む
筆者の家庭でよく使っていたのが「氷」。子どもが学習中にウトウトし始めたとき、氷をひとつ渡して噛ませると、一気に目が覚めることがありました。
冷たさ+噛む動作のダブル刺激で、短時間ながらも集中が戻る体験をこれまでに何度もしており、今でも困ったときはこの方法を使うようにしています。
また、朝の登校前など、なかなか目が覚めない時にも氷を活用することがありました。
寝起きが悪く、声をかけても反応が鈍いときに、氷をひとつ口に入れてあげることで覚醒の助けになったことが何度かあります。
もちろん、驚かせるのではなく、必ず「氷食べる?」と声をかけて、子どもが同意したうえで行うことが大切です。
※氷を使う際は、できるだけ小さめ〜中くらいのサイズで、角のとがっていないものを選ぶようにしましょう。大きくて尖った氷は、口の中を傷つける可能性があるため避けたほうが安心です。少量の水で溶かしておくのも◎。
▷ キシリトールガム
氷が難しい場面では、キシリトール入りのガムを噛むのもおすすめです。
筆者自身も勉強中によくガムを噛んでおり、眠気を感じたときのリセットとして重宝していました。
噛む動作が脳を刺激し、集中力が戻るだけでなく、虫歯のリスクも低く、毎日の習慣として取り入れやすいという利点もあります。
※お腹がゆるくなる場合もあるので1日の量にご注意ください。
2. 軽いストレッチや体の動き
じっと座っていると血流が滞り、酸素の供給が少なくなって眠くなりがちです。数分間の軽いストレッチや、簡単な体の動きでも、脳への酸素供給が改善され、眠気が緩和されます。
たとえば、小学生でも簡単にできるものとしては、以下のような動きが効果的です。
- 首を左右・前後にゆっくり回す
- 肩をぐるぐる10回まわす
- 手を上に伸ばして背伸びする
- その場でジャンプを5〜10回する
- 深呼吸をゆっくり3回行う
いずれも机のそばででき、短時間で体をリフレッシュできる方法です。
身体活動は思考力や学習力の向上に寄与することが示されています(引用元:厚生労働省『健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(アクティブガイド2023)』)
筑波大学の研究でも「10分間の軽度な運動が記憶力や注意力を高める効果がある」と報告されています(参考:Hirano et al., “Effects of chewing on cognitive performance”, Appetite, 2008)
3. タイマー学習でリズムを作る
集中が続かないときは、「タイマーを使って時間を区切る」ことが効果的です。
たとえば大人であれば「25分集中+5分休憩」のポモドーロ・テクニックが知られていますが、小学生、特に低学年の場合は、10〜15分程度の集中時間から始めるのが現実的です。
タイマーを使うことで「あと〇分がんばれば休憩できる」というメリハリが生まれ、眠くなる前にリセットのタイミングを作ることができます。
実際に学習前に「今日は10分やったら3分休憩しようね」と目標を決めることで、子ども自身もやる気を出しやすくなります。
ポモドーロ・テクニックは時間管理術の一つで、集中力の維持に効果があるとされる(参考:Francesco Cirillo『The Pomodoro Technique』)
4. 短時間の仮眠
保護者の方なら、強烈な睡魔に襲われたときに短時間の仮眠をとってやりすごすといった経験をされている方も多いのではないでしょうか?
実際、10~20分ほどの短い仮眠には、眠気をリセットし、集中力や学習効果を高める効果があるとされています。
国内でも仮眠を取り入れている教育現場があります。
たとえば熊本県立宇土中学校・宇土高等学校では、昼休み後に10分間の「ウトウトタイム」と呼ばれる仮眠時間を設け、生徒の集中力維持に役立てています(引用元:熊本県立宇土中学校・高等学校公式サイト)。
同様に、岐阜県大垣市立北中学校でも週に2回、10分間の「シエスタ(仮眠)」を導入しており、オルゴールの音楽とともに机に伏せて休息する取り組みが行われています(引用元:岐阜県学校保健会「保健ニュース No.118」PDF)。
このように、短時間の仮眠は学校現場でも実践されており、学習への前向きな効果が期待されています。
筆者自身も15分の仮眠を日常的に取り入れており、高確率で眠気が軽減され、頭がすっきりとリフレッシュされるのを実感しています。
お子さんだけでなく、大人にとっても、短時間の仮眠は効果的なリセット方法といえるでしょう。
5. 刺激を変える(学習環境にちょっとした変化を加える)
長時間、同じ姿勢・同じ場所・同じ画面で学習を続けると、どうしても集中力が落ち、眠気が出てきてしまいます。タブレット学習中でも、環境に少し変化を加えることで、気分転換やリセットが期待できます。
たとえば、照明の明るさを変える、椅子ではなく立って学習してみる、背景の音(BGMや環境音)を軽く入れる、などの工夫が挙げられます。
外のほうが涼しい場合は窓を開けて外気に触れるのも有効です。
学習内容が変わらなくても、こうした周囲の刺激を切り替えることで、脳への印象や集中の持続に影響を与えることがあります。
また、タイミングを決めて一度席を立つ、学習場所を机からリビングテーブルに変えるなども効果的です。タブレットを活用するからこそ、学習スタイルを自由に切り替える柔軟さを活かしましょう。
保護者ができるサポートとして

お子さまの集中力や学習スタイルに合った教材を選ぶことも、眠気対策のひとつです。 「どんなタブレット教材が合っているかわからない」という方は、以下の記事も参考にしてみてください。
👉 【レベル別】小学生におすすめのタブレット学習教材ランキング9選
👉 中学生におすすめタブレット学習7選!比較ランキング【2025年最新】
子どもが「なんか眠い」「ぼーっとする」と感じたときに、「ストレッチしてみようか?」「ガム噛んでみる?」など、気軽に声をかけてみてください。ルーティンとして取り入れることで、子ども自身も自分で対処できるようになっていきます。
こうした小さな工夫が、学習習慣の定着や、タブレット学習そのもののストレス軽減につながります。
この記事は、筆者自身の家庭での経験と、教育現場・科学的根拠に基づいて構成されています。集中力の波と上手に付き合いながら、タブレット学習をより効果的なものにしていきましょう。
ご紹介した対策の中から、お子さまに合いそうなものをぜひひとつでも取り入れてみてください。小さな工夫の積み重ねが、大きな変化につながります。
参考文献
- 量子科学技術研究開発機構「ものを噛む“チューイング”、脳の作業記憶が向上」
https://www.qst.go.jp/site/qms/1631.html - ロッテ「噛むこと研究室」『噛むと脳が活性化する⁉ 噛むことと脳の関係とは…』
https://www.lotte.co.jp/kamukoto/brain/845/ - 厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(アクティブガイド2023)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001171393.pdf - Hirano et al., “Effects of chewing on cognitive performance” (Appetite, 2008)
- Francesco Cirillo『The Pomodoro Technique』
- NASA Technical Reports Server『Effects of Planned Cockpit Rest on Crew Performance and Alertness in Long-Haul Operations』(1995)
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19950006379/downloads/19950006379.pdf